がんの病気を知る
がん
がんとは
一般に癌や悪性新生物あるいは悪性腫瘍と呼ばれます。がんは、年齢とともにリスクが高まり、3人に1人が死亡するといわれて、日本人の死因第1位です。様々な病気のなかで最も死亡率の高い病気にもかかわらず、初期にほとんど自覚症状がありません。そのため、健康診断などで発見されることが多く、発見されたときにはすでに進行していたというケースも少なくありません。
がんの進行度はステージⅠ~Ⅳで表し、Ⅰが早期、Ⅳが最も進行している状態となります。またステージの判定は、がんの広がり(大きさ)、リンパ節へ転移の有無、多臓器への転移の3つの基準を元に分類されます。
ステージⅠ 腫瘍が筋肉の層まででとどまっており、リンパ節に転移はしていない状態
ステージⅡ リンパ節に転移はしていないが、筋肉の層を超えて浸潤している。または、リンパ節に少し転移している状態
ステージⅢ 腫瘍が筋肉の層を超えて深く浸潤しており、リンパ節転移もみられる状態
ステージⅣ 血行性転移が見られ、離れた臓器に転移している状態
原因
がんは未解明の部分が多い病気で、発生原因やメカニズムについても、まだ完全に解き明かされていません。遺伝などの先天的な体質や、生活習慣などが複雑に絡み合って発症する場合が多いと考えられています。
私たちの体は約60兆個の細胞からなっており、絶えず分裂し、新しく生まれ変わっています。その過程において、発がん物質などの影響で遺伝子が突然変化して、がん細胞ができます。ただし、すぐにがんになるわけではありません。それらが異常な分裂・増殖をくり返し、10~20年かけてがんになります。
がんの発生因子
・多量の飲酒
・喫煙
・塩分のとりすぎ
・果物・野菜不足
・熱すぎる食べ物や飲み物の刺激
・動物性食品のとりすぎ
・肥満
・ストレス
・遺伝
・ウィルス
主な疾患
大腸がん
男女ともに、急増しているがんです。増加の背景には食生活の欧米化が進んだためで、今後も増加するとされています。40歳頃から増え始め、高齢になるほどリスクが高まります。進行すると、血便のほか、便秘や下痢などの症状が現れますが、初期には自覚症状はほとんどありません。
胃がん
塩分やピロリ菌が最大の要因と言われ、塩分の濃い味を好む日本人に多くみられます。また50歳以上の日本人はピロリ菌に感染していると言われていますので、注意が必要です。ですが近年はピロリ菌の新たな感染が減ってきています。胃がんの初期は無症状のことが多く、進行すると胃痛や胸焼けなどが見られます。一方、進行すると胃の入り口付近のがんの場合に、食事がのどを通らなくなってしまうことがあります。また、胃の出口付近のがんの場合、胃の中に食べたものがたまり、わずかな量の食事でもおなかが張ってくる感じがすることがあります。
肺がん
男女ともに死亡数の多いがんで、発見が遅くなるほど死亡率が高くなります。最大の要因は喫煙です。喫煙者が肺がんになるリスクは非喫煙者と比べて5~20倍とも言われています。早期では自覚症状がほとんどなく、あっても咳や痰などかぜの症状に似ているため受診されるケースは少なく、健診などで見つかることが多くあります。
肝臓がん
肝臓は「沈黙の臓器」とも言われ、がんができてもよほど進行しない限りは症状があらわれません。がんが進行すると、腹部のしこりや圧迫感、痛み、おなかが張るなどの症状を訴える人もいます。B型肝炎やC型肝炎から発症することがほとんどですが、肝硬変や慢性肝炎から発症することもあります。
前立腺がん
男性特有のがんです。50歳代から増え始め、年齢を重ねるほど発症リスクが高まります。初期にはほとんど自覚症状がなく、進行すると尿が出にくい、尿の回数が増える、排尿後の残尿感などの症状が出現します。
乳がん
日本人女性がかかるがんのなかで最も多いがんで、徐々に増加傾向です。20歳代から増え始め、40歳代後半から50歳代にピークを迎えます。初経年齢が早い、閉経年齢が遅い、出産歴がない、初産年齢が遅い、授乳歴がないことがリスク要因とされています。普段感じなかったしこりが出現したり、乳頭からの異常分泌、乳頭や乳輪がただれるなどの自覚症状があります。
子宮がん
20歳代から40歳代後半に多くみられます。いずれのがんも初期には自覚症状がほとんどありません。疑う症状としては、生理とは関係の無い出血やおりものがあったり、排尿しづらい、または、排尿するときに痛みがある。あるいは下腹部や腰が痛いといったことです。
検査・診断
内視鏡検査
カメラのついた細い管を体の中に挿入し、消化管や気管、大腸などを体の内側から観察する方法です。
代表的なものには胃カメラなどがあり、病変部位を直接観察できるため、がんの早期発見に非常に有効です。さらに、初期がんであれば、その場で切除根治できる場合もあります。
CT検査
体の周りからX線を照射し、体の断面画像を観察する方法です。機器にあおむけになり、そのまま筒状の機械の中を通過して撮影します。
MRI
強い磁気を当て、体の断面画像を観察する方法です。様々な角度の断面を見ることができる特徴があります。
腫瘍マーカー
尿や血液中の「腫瘍マーカー」の値によって、特定部位のがんを診断する方法です。ある程度進行したがんでないと「腫瘍マーカー」を作り出さないため、がんの早期発見にはつながりません。
治療方法
現在のがんの治療は、外科的治療、放射線治療、化学療法の3つの治療法を組み合わせる集学的治療が主流になっています。
外科的治療
いわゆる手術により病巣を取り切って、がんの根治目指す治療方法です。
放射線治療
治療に用いられる放射線は、X線、γ(ガンマ)線、電子線、新しいものでは、陽子線や重粒子線があります。
メリットとしては、体にメスを入れることないため、美容的に優れています。しかし、副作用があるため放射線治療を行うかどうかや、どのように行うかの検討が必要です。
化学療法
抗がん剤を用いた治療法です。手術療法や放射線療法のような局所的な治療に対して、化学療法は広範囲に治療の効果が及びます。飲み薬と点滴や注射で注入する方法があります。
膵臓がん
膵臓とは
膵臓は胃の後ろ側に位置し、十二指腸とつながっています。形状は細長く接続部から頭部、体部、尾部に分けられます。膵臓の働きは主に消化酵素を含んだ膵液を分泌する外分泌機能と、血糖の調節に必要なホルモンを分泌する内分泌機能に分けられます。内分泌機能は膵臓にあるランゲルハンス島という部分が担っています。また膵液は膵管を通って十二指腸に分泌されます。非常に大事な血管が多い臓器です。
膵がんとは
膵がんとは、ほとんどが膵管から発生する膵管がんのことで膵がん全体の9割を占めています。膵がんは消化器のがんの中で最も治療成績が悪いがんの1つです。がん罹患者における死因は現在5位です。男性にやや多く、50歳以上になるとその発生頻度は増加します。膵がんは十二指腸つながっている方から、膵頭部がん、膵体尾部がん、膵全体がんに分けられます。特徴的な初発症状がなく、膵がんと診断された時にはすでにがんが進行し、他臓器に転移している場合が多いです。手術が唯一の根治治療ですが、7割から8割は手術の適応にならない、もしくは切除が可能であっても手術後の早期再発率が高い傾向にあります。膵がんには他に、嚢胞を形成するがん、粘液分泌が盛んながん、ランゲルハンス島が原発のがんなど、比較的予後の良いものもあります。
膵がんの治療成績向上のポイントは、早期発見・早期治療です。最近は技術の進歩により、早い時期の膵がんが見つかるようになり、治療成績も向上しています。
発生要因
膵がんの発生要因としては、食の欧米化や喫煙などの生活習慣、排気ガス・化学物質などの環境要因が挙げられますが、こういった要因と膵がん発症との関係性ははっきりとは証明されていません。しかし最近の研究で、慢性膵炎や糖尿病、家族内に膵がん罹患者がいると危険性が増すと指摘されます。
症状
初期症状はほとんどありません。進行するにつれて腹痛や黄疸、食欲不振、背部痛、倦怠感、体重減少などが現れます。なお、糖尿病の発症や糖尿病の急な悪化が膵がん発見のきっかけとなることも多いです。
膵がんの症状は乏しいものの発症場所により、病状の特徴が異なります。膵がんの60%は頭部にできますが、頭部は胆管が通っているため、がんで狭窄してしまい胆汁の流れが悪くなることで、黄疸が生じやすくなります。体部や尾部では、頭部と比べて胆管に影響が及びにくいため黄疸も出現しにくく、発見はさらに遅くなる傾向にあります。診断された時点では、手術不能という場合も多くあります。症状としては、便秘、下痢など一般的な消化器疾患と勘違いしやすく、たまたまCTや超音波検査をされた場合に見つかることも少なくありません。また、慢性膵炎の症状ともよく似ており、膵がんの発見はさらに遅くなる傾向にあります。
検査・診断
膵がんの検査は、主に内視鏡検査、血液検査、画像検査、組織検査に分けられます。
内視鏡検査
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)
十二指腸内視鏡を用いて検査を行います。内視鏡の先端を十二指腸に留め、十二指腸乳頭部に細い管を介して造影剤を注入し、膵管や胆管をX線撮影します。その際に、一部組織を採取する場合があります。
血液検査(腫瘍マーカー)
膵がんがあると、血液中の膵酵素が異常値を示すことがあります、発症していることが前提になるので早期発見には不向きです。
画像検査
膵がんの診断を行う上でたいへん重要な検査です。代表的なものは腹部エコー、CT、MRIです。特に、腹部エコーは容易に実施でき、膵病変のスクリーニング検査としてとても有用です。最近では、慢性膵炎と識別するためにPET検査も盛んに行われるようになっています。これらの画像検査は、ある程度の大きさにならないと発見できないため、本当の意味で早期がんを発見することはできません。早期で膵がんを発見するためには、膵管の拡張や小嚢胞といった間接的な所見を慎重に調べなければいけないと言われています。
組織診断
細胞または組織を採取して、病理医が顕微鏡で観察します。方法はいくつかあります。X線や超音波のもとで細い針を膵臓内に挿入し細胞を採取したり、腹腔鏡手術にて組織を採取します。
治療方法
外科的治療(手術)
膵臓は、胃や十二指腸など他の臓器と隣接しているため、膵臓だけを摘出することは少なく、周辺臓器も部分的に一緒に切除します。周囲には重要な血管もたくさん通っており、血管を切って吻合する必要が出てくるため、手術難易度はかなり高いです。膵がんの手術方法は、基本的にはがんの部分だけ摘出するのではなく、がんが広がっている可能性のある周辺の臓器やリンパ節を一緒に摘出します。切除範囲は、がんの存在する部位によって異なります。
膵頭十二指腸切除術
消化器系の手術の中で最も複雑な技術を要する手術であり、(胃)十二指腸、胆管、胆のうを含めた膵頭部の切除と胆管再建、血管にがんが広がっている場合は血管の一部も切除しますので血管外科の技術が必要になります。通常は、周辺のリンパ節の摘出も同時に行います。切除後は小腸と残った膵臓を縫い合わせ、膵液が小腸に流れるようにします。手術時間は8時間~10時間かかることがあります。
膵体尾部切除術
膵体部および尾部のがんの場合、膵臓の体部と尾部を切除します。通常は脾臓も摘出されますが、消化管の再建は必要ありません。術後の合併症としては、膵管空腸吻合部の縫合不全などの消化管縫合不全、膵断端からの膵液漏、糖尿病や消化吸収障害があります。
バイパス手術
姑息的治療として、胆管が狭窄・塞がり黄疸が出ている場合は、黄疸を解消するために胆管と小腸をつなぐバイパス手術(胆管空腸吻合バイパス術)を行ないます。また、十二指腸が狭窄・塞がっている場合は、食事ができるように胃と小腸をつなぐバイパス手術(胃空腸吻合バイパス術)を行います。
化学療法
抗がん剤
根治手術が不可能な場合や手術後に再発が認められた場合、抗がん剤による治療が行われます。ある程度決まった投与量や間隔でいくつかの薬を組み合わせて使うことが多く、ほとんどが点滴で投与されます。近年の医療技術の発展により、手術できない状況にあった患者様でも、抗がん剤が著しく効いたことで手術が可能となるケースも出てきています。
放射線療法
放射線治療
通常、抗がん剤と併用して行われることがほとんどで、手術が不可能でがんが局所のみに広がっている場合に行われことがあります。現在のところ、放射線療法のみで延命効果が得られとする確立された報告はありません。
肺がん
肺とは
肺は呼吸をつかさどる気管で、右肺は上葉・中葉・下葉の3区域、左肺は上葉と下葉の2区域に分けられます。鼻や口から吸いこんだ空気中の酸素を体内に取り込んで、二酸化酸素を体外へ出すという重要な働きをしています。さらに細かく言うと肺の中には肺胞と呼ばれる小さな袋状の中に入っていき、そこで血管内へ取り込みと排出が同時に行われます。
肺がんとは
肺がんは、日本人におけるがん死亡率1位です。男女別では、男性1位、女性2位です。肺がんは大きく2つに分類され、小細胞がんと非小細胞肺がんと呼ばれます。それぞれ特徴や有効な薬の種類が変わってきます。肺がん全体のうち小細胞肺がんが10~15%を占め、非小細胞肺がんは80~90%です。小細胞肺がんはがんの進行スピードは速いですが、抗がん剤や放射線治療の効果を比較的えやすいです。非小細胞肺がんは、さらに組織型によって、扁平上皮がん・腺がん・大細胞がんなどがあります。非小細胞は進行のスピードが速くないため、早期発見ができ、手術で完全に切除できれば完治する見込みがありますが、抗がん剤や放射線治療は効果が得にくいです。
発生要因
肺がんの最大の発生要因はタバコですが、アスベスト、ヒ素などの生活環境に起因するものあります。タバコには約60種類の発がん物質が含まれており、肺や気管支が喫煙のたび発がん物質にさらされることにより細胞に遺伝子変異が起こり、この遺伝子が変異した細胞が増加しがんになります。
症状
初期症状はほとんどありません。進行しても、咳や胸痛、呼吸困難、体重減少、血痰、骨痛、むくみなど肺がん特有の症状はありません。そのため早期発見が難しいと言われます。
検査・診断
肺がんの検査は主に、画像検査、血液検査、組織検査に分けられます。
画像検索
胸部レントゲン検査
胸部を正面や側面から見る検査ですが、心臓や骨と重なった部位の病変や小さな病変の発見は難しいです。
CT・MRI検査
エックス線や磁気を使用し、コンピュータで計算して胸部の詳細な画像を作成し、診断する方法です。肺がんでは影がCTよりぼけやすいので使用吸うことは少ない。
PET検査
ブドウ糖に少量の放射性物質を添付し、静脈へ注射します。放射性物質が集まっているところががん病変部位です。がんがブドウ糖を大量に消費する性質を利用した検査方法です。
血液検査
腫瘍マーカー
血液検査を用いてがんを患うと正常より高い数値を示す物質を検知する方法です。
組織診断
痰の細胞やその他の組織を採取して、病理医が顕微鏡で観察します。あるいは、手術室で実際に肺の組織を採取する場合があります。
治療方法
外科的治療(手術)
肺を切り取ることでがんを切除します。がんの位置や大きさによって手術方法が変わります。小さい部分だけを切り取る手術を区域切除あるいは楔状切除といい、さらに切除範囲を広げると肺葉切除と呼ばれます。稀に片肺をすべて取ってしまう場合があり、肺全摘術といいます。また、ほとんどの手術でリンパ節を切除し、がんが転移しているかどうか調べます。
胸部を大きく開けて行う開胸手術と数か所小さく皮膚を切開し、その穴からカメラを入れて行う胸腔鏡手術がありますが、最近は胸腔鏡を用いる症例が増えています。2018年度診療報酬改定により、ロボット支援下内視鏡手術が保険適用になっています。
化学療法
抗がん剤
肺がんの場合プラチナ製剤とよばれる薬剤といくつかの薬を組み合わせて使うことが多く、点滴や内服で投与されます。近年の医療技術の発展により、手術できない状況にあった患者様でも、抗がん剤が著しく効いたことで手術が可能となるケースも出てきています。
放射線療法
放射線療法
多くの場合化学療法と並行して行われます。手術ができない場合の進行抑制を目的に行ったり、手術との併用、抗がん剤による化学療法と併用することもあります。
肺がんに対する放射線療法では、肺炎や食道炎、皮膚炎などが起こることが少なくありません。これは、放射線による一種の火傷と考えられます。
乳がん
乳がんとは
乳がんは乳房にできる悪性腫瘍で、日本人の12人に1人が乳がんと診断されています。※1現在もなお、患者数は増加傾向にあり、40歳代後半から50歳代にピークを迎えます。また男性にも発生する可能性はありますが稀なケースです。そのうち約90%は乳管(母乳の通り道)から発生し、「乳管がん」と呼ばれます。残りの約10%が小葉(母乳を産出する場所)から発生し、「小葉がん」と呼ばれます。早期に発見の場合は、90%以上は治ります。乳がんは、しこりとして見つかる前に、乳房の周りのリンパ節や、骨、肺、肝臓、脳などに転移して見つかることがあります。
※1人口動態統計2015年(厚生労働省大臣官房統計情報部編)
発生要因
乳がんは、女性ホルモンのエストロゲンという物質が関与していることが知られています。初潮が早い、閉経が遅い、初産年齢が遅いまたは高齢で未産、経口避妊薬の使用や閉経後の女性ホルモン補充療法など、エストロゲンにさらされる期間が長いことが乳がんにかかりやすい条件として挙げられます。あるいは、脂肪組織でエストロゲンがつくられるため、高脂肪食、肥満なども関与しています。もともと欧米に多かった乳がんが日本で増えているのは、ライフスタイルや食生活の欧米化が大きく影響していると考えられます。がんは未解明の部分が多い病気で、まだ完全に解き明かされていません。遺伝などの先天的な体質や、生活習慣などが複雑に絡み合って発症する場合が多いと考えられています。
症状
代表的な症状は、乳房にできるしこりです。その他に痛みや赤みが挙げられます。さらに目に見える変化としては、乳頭部分のただれや湿疹、乳頭からの異常分泌が見られることもあります。症状が進行するとがんの周辺の組織がひきつれて、乳房や乳頭が変形することもあります。乳がんと似た症状に乳腺症や乳腺炎などがありますが、自分で判断せずに、しこりや痛みを感じた場合は医師に相談しましょう。
検査・診断
マンモグラフィ、(トモシンセシス)
乳房専用のX線撮影装置で、乳がんの早期発見に欠かせない最も有効な画像診断の1つです。乳がんの初期症状である石灰化や乳腺の全体像をとらえやすい一方で、検査の方法上痛みを伴うことがあり、年齢・乳腺量の個人差により、詳細な診断ができないことがあります。また、被曝するため妊娠中や疑いがある場合は検査不能です。
乳房超音波(エコー)、エラストグラフィ
被曝がないため妊娠中でも検査可能です。さらに、痛みを伴わないため、比較的受けやすい検査で、小さなしこりやしこりの質的診断をしやすいです。ですが、がん以外の良性腫瘍の所見も見つかりやすく、再検査となる可能性が高いです。また、施行者の技量に依存する部分が大きいというデメリットがあります。
穿刺吸引細胞診、分泌物細胞診、組織診
乳がん検診を受けて「要精密検査」だった場合に行われる場合が多いです。病変部位をを採取して診断をする方法です。
治療方法
外科的治療(手術)
乳房部分切除術(乳房温存手術)
がんの大きさが3㎝以下、検査でがんが広範囲に広がっていないことが確認された場合に、乳房の一部のみを切り取り乳房のふくらみや乳首を残す方法です。術後は、がんが残っている場合があるので放射線をあてるのが一般的です。
乳房切除術
がんの大きさが3㎝以上や3㎝以下でも周囲に広がっている場合に、内側の筋肉は残して、乳房全部をがんとともに摘出する手術です。しかし、近年では自分の組織(背中の脂肪など)やインプラントを挿入して乳房の形を再建できるようになりつつあります。
化学療法
ホルモン療法
乳がんの特徴的な治療法で、要因である女性ホルモン(エストロゲン)を産出したり、受容する細胞に対して作用する薬剤を使用します。 この治療方法は、がんを直接的に退治する抗がん剤に比べると副作用は穏やかです。主な副作用は、発汗や、めまい、不眠、体重増加、骨量の低下などがあげられる。
抗がん剤
ある程度決まった投与量や間隔でいくつかの薬を組み合わせて使うことが多く、ほとんどが点滴で投与されます。
大腸がん
大腸がんとは
大腸は全長2メートルほどあり、口側から上行結腸(右腹部)、横行結腸、下行結腸(左腹部)、S状結腸、直腸に分けられます。がんで大別するなら結腸がんと大腸がんに分けられます。日本人において発症が多い部位はS状結腸と直腸です。なお女性においては死因の第1位です。
発生要因
動物性脂肪やたんぱく質を摂取すると分泌される胆汁酸が分泌されます。この胆汁酸には発がん物質を含んでいると言われます。食の欧米化により、動物性脂肪やたんぱく質の過剰摂取をする頻度が多くなったことで大腸の粘膜にがんが発生しやすくなったといわれています。あるいは、アルコールの過剰摂取もがんの発生要因の1つとされています。また若年性でのがんの場合は、遺伝的な要素も考えられます。
症状
初期の代表的な症状は、血便、下血、下痢、便秘です。あるいは便が細い、残便感、おなかが張る、貧血、体重減少があります。進行したがんでは部位により症状が異なります。上行結腸がんの場合は、症状がでにくく、かなり進行したころに下腹部にしこりが発生したり、貧血の症状が現れます。下行結腸がんでは血便や血塊が出る症状があります。直腸がんの場合は、肛門に近いため血が直接でてきます。直腸がんの場合の症状は痔と勘違いされやすく、発見が遅れる恐れがあります。
検査・診断
直腸触診
肛門から指を入れてしこりや腫瘍がないかを判断します。
注腸造影検査
前日までに腸内をきれいにして、肛門から直接造影剤を注腸しレントゲンをとります。撮影後、フィルムによる画像診断を行います。
大腸内視鏡検査
腸内をきれいにした後、肛門から先端にカメラのついた管を挿入し、腸の内側を直接観察します。腫瘍の大きさや数にもよりますが、がんが発見された場合、その場で切除をすることが可能です。
CT・MRI検査
X線や磁気を使用して、おなかの中を撮影します。終了後、画像を様々な断面から観察し、診断をします。
腫瘍マーカー
血液から大腸がんの腫瘍マーカー検査を行います。
PET検査
がんは活動するのに大量のブドウ糖を使います。この動きを活用した検査方法です。ブドウ糖を含む放射性薬物を体内に投与し、その過程を特殊なカメラでとらえて画像化します。ブドウ糖の吸収状況に応じて、診断されます。
治療方法
外科的治療(手術)
内視鏡的手術
大腸内視鏡検査時にその場で腫瘍を切除してしまいます。浸潤の具合で術式は変化します。
結腸がん手術
病巣から10㎝ほど離れた場所で腸管を切断します。その後切断した腸管の吻合( 管と管をつなげる作業)を行います。
切り取る場所によって名称が変わります。
回盲部切除術、右半結腸切除術、横行結腸切除術、左半結腸切除術、S状結腸切除術
直腸がん
直腸を局所的に切り取ります。
アプローチする場所によって術式名称が変わります。
経肛門的切除、経仙骨的切除、経括約筋的切除
直腸切断術
直腸周辺には生殖器や排便・排尿に関係する大切な神経や血管が多数あるため、難易度が高い手術になります。直腸を周辺の臓器(肛門括約筋など)から切り離し、切断します。腹膜反転部より上で吻合するか下で吻合するかで術式の名称が変わります。
高位前方切除術、低位前方切除術
大腸を手術する際、大きくお腹を開けて手術を行う開腹手術と、皮膚に多数の小切開を加えて手術を行う腹腔鏡手術があります。直腸切断術を腹腔鏡で行う場合は術者の技術度が高くないとできません。腸を取り出す際に、おなかを少しだけ開ける場合があります。また、腸の状態によっては人工肛門を造る場合があります。
化学療法
抗がん剤
ある程度決まった投与量や間隔でいくつかの薬を組み合わせて使うことが多く、ほとんどが点滴で投与されます。近年の医療技術の発展により、手術できない状況にあった患者様でも、抗がん剤が著しく効いたことで手術が可能となるケースも出てきています。
放射線療法
直腸がんにおいて、手術前にがんのサイズを小さくし、がん根治率向上を目的で放射線治療が行われることがあります。または他の臓器に転移してしまい、手術の難しい骨盤内のがんによる疼痛コントロールのために行われます。
放射線療法の時期は手術前・手術中・手術後の3パターンがありますが、手術前に照射することが一般的です。また、抗がん剤治療と一緒に行うこともあります。
前立腺がん
前立腺とは
前立腺は男性特有の臓器で、精液の一部を作っています。大きさはクルミほどで、膀胱の下にあり、尿道を取り囲むように存在しています。また、直腸と隣接しているため、発症すると排便や排尿機能に影響を及ぼしやすいです。
前立腺がんとは
前立腺がんは、アメリカでは罹患者数が1位、死亡者も2位ともっとも多いがんのひとつです。日本においては、罹患者数は増加傾向にありつつも、治療成績は高いため死亡率はそれほど高くなく、全体のがん罹患者のうち死亡率は5%ほどです。増加の要因としては、加齢に伴う要因が大きいので平均寿命が延びていることが前立腺がん患者数の増加要因の1つですが、検査精度があがり早期のがん発見数が伸びているからとも言われています。発症は60歳ぐらいから急増し、加齢に伴って発症率も増加します。また前立腺の位置上、リンパ節や骨盤に転移しやすいがんです。
発生要因
前立腺がんの発生要因としては、飲酒、喫煙、食の欧米化に伴う高たんぱく・高脂質の過剰摂取、加齢と言われます。
症状
初期症状はほとんどありません。進行すると、前立腺は尿道を取り囲むような構造をしているため、排尿障害が発生します。具体的には、トイレに行く回数が増える・尿の切れが悪い・いきまないと出ないなどです。そのほかにも、失禁、血尿、尿意はあるが出ない等が挙げられます。
検査・診断
前立腺がんの検査は主に、血液検査、触診、画像診断、組織検査に分けられます。
血液検査
腫瘍マーカー
前立腺がんは研究が進んでおり、腫瘍マーカーの中で最も有用なPSA(前立腺特異抗原)検査が行われます。少量の血液を採取するだけで、がんの進行度、治療効果の判定、再発の診断、予後の予測までできます、しかし、確定はできないので最後は組織検査により確定します。
触診
古くからおこなわれている診断方法です。前立腺は直腸と隣接していますので、経肛門的に触診します。ですが、ある程度の大きさにならないと触れることはできません。
画像診断
MRI
近年急速に進化している検査方法で、高い精度で前立腺がんを発見できます。
組織診断
局所麻酔(腰椎麻酔)、や全身麻酔を行い、エコーを用いて組織を採取します。その際は専用の自動生検装置(前立腺生検用の針)を使います。採取した組織を顕微鏡で観察し、がんの有無やがんの悪性度を判断します。
治療方法
外科的治療(手術)
前立腺がんに対して手術を行う場合は、ほかのがんとは違い基本的に部分切除ではなく、前立腺全摘除術になります。小さな臓器なので部分的に切除するのが難しいことと、全摘出しても命に関わりがないということが理由として挙げられます。一般的には周囲のリンパ節も予防的に摘出します。
下腹部を大きく開けて行う開腹手術と数か所小さく皮膚を切開し、その穴からカメラを入れて行う腹腔鏡手術がありますが、最近は腹腔鏡を用いる症例が増えています。2012年の診療報酬改定により、ロボット支援下内視鏡手術が保険適用になっています。
内分泌療法(ホルモン療法)
内分泌療法
前立腺がんは男性ホルモンで病気が進行する性質があるため、ホルモンの分泌、働きを抑制する薬によって前立腺がんの進行を抑える方法です。
化学療法
抗がん剤
内分泌療法で効果が効かなくなった場合に行われます。前立腺がんの抗がん剤治療の場合、がんの根治をめざすわけではなくがんの増殖や痛みを抑える消極的治療方法になります。
放射線療法
放射線療法
多くの場合化学療法と並行して行われます。一般的ながんとどうような治療方法もありますが、前立腺がんの場合、限られた条件限られた施設にはなりますが、小線源療法という独特の方法があります。放射線を出す物質を小さなカプセル状のものにつめ、前立腺の中に入れて、体内から照射する方法です。病変した組織の近くに留置できるため非常に高い線量を照射することができます。
胃がん
胃がんとは
胃がんは、がんによる死因のうち2位を占めます。胃は、食道と十二指腸(小腸)をつなぐ袋状の器官で食べ物を一時的に蓄えたり、消化したりする役割があります。食道につながる方を噴門部、小腸とつながる方を幽門部といいます。胃の構造は、内側から粘液や胃液を分泌する粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜の5層構造でできています。この層のどこまでがんが浸潤したかによって呼び方が変わります。胃の粘膜、粘膜下層までの浸潤であれば「早期がん」、それより浸潤が進むと「進行がん」といいます。早期がんであれば、ほとんどの場合で完治させることができます。
発生要因
胃がんはすでに多くの研究が行われており、いくつかの発生要因が指摘されています。喫煙、野菜、果物の摂取不足や塩分の多い食品の摂取といった食生活などの生活習慣とヘリコバクターピロリ菌の感染などが胃がん発生のリスクを高めるといわれています。食生活については、の過剰摂取が指摘されています。
ピロリ菌
正式名称を「ヘリコバクターピロリ」といいます。だいたい5歳ぐらいまでに感染するといわれています。ピロリ菌はもともと環境衛生が良くない場所に生息していますが、生活インフラが整備された現代では生水を飲んでも感染することはほとんどないです。最近の研究結果では、母から子などの家庭内感染が疑われています。実際、50歳代は50%以上感染しているといわれていますが、30歳代で15~20%、20歳代だと10%以下だと言われています。
ピロリ菌はアルカリ性のアンモニアを産生して胃の粘膜を刺激し、免疫反応により胃の粘膜に炎症を起こさせます。炎症が長期化すると、今度は胃潰瘍を起こします。そこからがんが発生するため、胃がんの原因の多くはピロリ菌といわれています。
症状
代表的な症状は、胃周辺の違和感・不快感、みぞおち周辺の痛み、胸やけ、食欲不振、吐き気などがあげられます。発見されずに進行していくと、黒い便(タール便)や吐血が起こりますが、ほとんどの場合、こういった症状が出る前に胃カメラなどの健康診断で発見されます。
検査・診断
胃X線検査
俗に言うバリウム検査です。バリウム(造影剤)と胃を膨らませる発泡剤を飲んで、体位を変えながらレントゲン撮影をしていきます。フィルム画像にて診断を行います。
胃内視鏡検査
小型のカメラが先端についた管を口または鼻から挿入し、食道、胃、十二指腸を胃の内側から直接観察していきます。腫瘍の大きさや数にもよりますが、その場で切除してしまうことができる場合があります。
腫瘍マーカー
胃がんでも腫瘍マーカーがいくつか確認されており、検査・診断できるようになっています。
治療方法
外科的治療(手術)
内視鏡的手術
先述した胃内視鏡を用いてその場で切除してしまう方法です。腫瘍の浸潤具合によって、切除の仕方が変わります。ポリベクトミー、内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)のなどの術式があります。
胃局所切除術
胃の一部をくり抜くように切除を行い、がんを取り除く手術です。
胃部分切除術(噴門側切除、分節切除、幽門側切除)
胃を大きく切除する術式で、切除する部位によってそれぞれ名前があります。食道側の胃を切除する場合を噴門側胃切除術、胃の体部を切除する場合を分節切除術、十二指腸側を切除する場合を幽門側胃切除術といいます。それぞれがんができた場所・進行の具合によって術式が選択されます。
胃全摘術
胃をすべて取ってしまいます。代替えとして食道と小腸をつなぎ、その間に胃の代わりとなる袋を作成する手術です。
病変部位を切除した後はそれぞれ端と端の管をつなぐのですが、つなぎ方は様々ありそれぞれに名前がついています(ルーワイ法など)。また、術式は決まってもおなかを大きく開けて手術を行う開腹手術と、お腹の皮膚を数か所小さく切開して、そこに5㎜~12㎜の管を通し、その管に特殊な長い器械を入れて行う腹腔鏡下手術を行う場合があります。腹腔鏡手術の方が、切開創が小さいため術後の美容的には優れていますが、手術時間が伸びる・高度の技術が必要になるなどメリットデメリットがあり、どちらの方がいい悪いということはなく、病巣の状況にと患者様に容態に応じて使い分けられます。
化学療法
抗がん剤
ある程度決まった投与量や間隔でいくつかの薬を組み合わせて使うことが多く、点滴や経口で投与されます。
免疫療法
人間の体には、細菌やウィルスの侵入を防いだり排除すしたりする免疫という仕組みが働きます。がんによって免疫が弱まったり、がんが免疫から逃げる術をつけてしまうと、この仕組みが働かなくなります。そこで弱った免疫を高めたり、がんを逃さないようにする薬を使ってがんを消滅させてしまう治療です。ですが、まだまだ研究の余地があり、今後が期待されている治療法です。
白血病
白血病とは
白血病は血液のがんです。血液細胞には赤血球、血小板、白血球がありますが、これらの血液細胞が骨髄でつくられる過程で、がんになります。がん化した細胞(白血病細胞)は、骨髄内で増殖し、骨髄を占拠してしまいます。そのため、正常な血液細胞が減少し、貧血、免疫系のはたらきの低下、出血傾向、脾臓(血液を貯蔵しておく臓器)の肥大などの症状があらわれます。血球を作る細胞すなわち造血幹細胞が骨髄の中でがん化して無制限に増殖する病気です。
白血病は、急速に進行する急性白血病と、ゆっくり進行する慢性白血病に大きく二分され、さらにそれぞれ骨髄系細胞から発生する骨髄性白血病と、リンパ球系細胞から発生するリンパ性白血病に分けられます。それらは、急性骨髄性白血病 (AML)、急性リンパ性白血病 (ALL)、慢性骨髄性白血病 (CML)、慢性リンパ性白血病 (CLL) の4つに称されます。
治療は抗がん剤を中心とした化学療法と輸血や感染症対策などの支持療法に加え、難治例では骨髄移植や臍帯血移植などの造血幹細胞移植治療も行われます。
慢性骨髄性白血病では、初期の段階での自覚症状はありません。その理由は、慢性骨髄性白血病は進行が遅く、過剰につくられた血液細胞でも、ほぼ正常と同等の働きをすることができることが挙げられます。そのため、多くの場合は、健康診断などで白血球数の増加を指摘されるなど、偶然見つかることになります。
しかし、ある程度進行すると、白血球や血小板が増加し、貧血や全身の倦怠感、無気力になるなどの自覚症状がみられるようになります。
一般的な「病気」は、急性期から慢性期へ移行することが一般的ですが、基本的には、初期の頃の状態、ゆっくりと病気が進行する時期を「慢性期」とよびます。ここから特に合併症などが無い場合には、数年後に「移行期」と呼ばれる時期になり、さらに数年後に「急性期」へと移行します。中には、移行期を経ずに、慢性期から急性期へ移行することもあります。症状が少なく、ゆっくりと進行する慢性期から、急激に症状が悪化する急性期へと移行してしまいます。
慢性骨髄性白血病の場合、治癒を目的とした化学療法というよりは、発熱や倦怠感、肝臓や脾臓の腫れなどのような症状の緩和と、血球数を抑えることを目的として、化学療法を行います。投与方法は、内服や点滴による静脈注射、筋肉注射などの方法があります。しかしこれらの方法では、脳脊髄液への薬剤の移行が困難であることから、抗がん剤を直接脊髄へ注射にて投与する「髄注」という方法をとることもあります。
分子標的療法
<特徴>
化学療法よりも高い治療効果が望めることから、慢性骨髄性白血病治療の第一選択ともいわれる治療法です。使用する薬剤としては、イマチニブ・ニロチニブ・ダサチニブという薬剤の、いずれかを選択します。1日1回内服し、治療効果を見ながら、薬剤の増量や変更、または継続を検討していきます。通常は、2~3ヶ月程度で白血球数が減少し、これに伴い、フィラデルフィア染色体を有する白血病細胞白血数も減少していき、白血数は正常化してきます。悪性の細胞が完全に消失する確率は40~60%程度と報告されています。
しかし、内服薬は生涯のみ続けなければならないこと、飲み忘れると効果が格段に低くなるという欠点があります。現在、内服薬を中止しても治療効果が薄れることが無いかどうか、新たな臨床試験が行われています。
インターフェロン療法
<特徴>
生物学的製剤であるインターフェロンを投与することによって、白血病細胞の数の減少だけでなく、白血病細胞そのものが根絶できる可能性がある治療法です。分子標的治療が開発される以前によく行われていた治療方法です。一般的には、化学療法と併用して行われることが多くなります。また、現在でも医療機関によっては第一選択とされる治療方法です。約75%で血液学的寛解がみられ、50%以上でフィラデルフィア染色体陽性細胞の減少を認める細胞遺伝学的効果が得られた、という報告があります。
しかし、その効果が永年持続するか、現在のところは明らかになっておらず、副作用が強く出ることや、治療に対する治療費が高額であるなど、いくつかのデメリットもあります。
造血幹細胞移植
<特徴>
造血幹細胞移植とは、正常な骨髄と患者さんの骨髄を入れ替える治療で、完全治癒が見込める唯一の治療法と言われています。大量の放射線や化学療法で正常な血液細胞と白血病の細胞を全て破壊した後、正常な骨髄を輸血のように投与し、破壊されている白血球と入れ替えます。若年層に対して行われることが多い治療法ですが、近年では移植前の化学療法を緩和し、高齢者でも行える治療法となりつつあります。
移植方法には、自家移植と同種移植、臍帯血移植があります。
・自家移植
自家移植とは、化学療法により腫瘍細胞が消失し、自身の正常血液細胞が回復した状態の時に自分の造血幹細胞を採取して凍結保存し、その幹細胞を移植する移植方法です。血液の回復が早く、高齢者でも受けられるという特徴があります。
・同種移植
同種移植とは、白血球の型が全て一致する「骨髄提供者の骨髄」を移植する方法です。しかし、型が全て一致する他人と出会える確率が非常に低いため、行われる頻度も少ない治療法となります。また、治療後の副作用が強く出ることがあり、血液の回復にも2~3週間ほどの時間が必要となることが特徴です。
・臍帯血移植
臍帯血移植とは、胎児の臍帯血を用いて、移植を行う方法です。臍帯血の特徴として、幼若で増殖能力に富む造血幹細胞が含まれていることが挙げられます。移植後の副作用が少なくて済み、高齢者でも行うことができる治療方法です。
いずれの方法でも、骨髄(または臍帯血)の移植後は、副作用があります。特に移植後1~3週間は易感染状態(感染しやすい状態)となるため、徹底的な無菌管理が必要となります。中には造血幹細胞移植に関連した合併症により、死亡する例もあります。
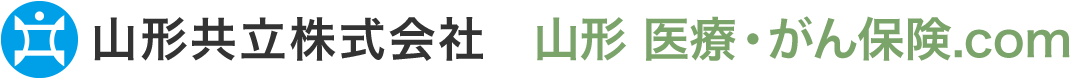
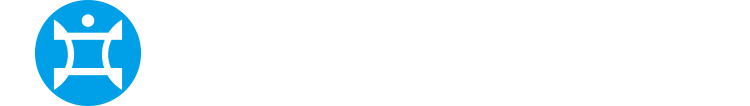 山形県で医療・がん保険相談なら
山形県で医療・がん保険相談なら

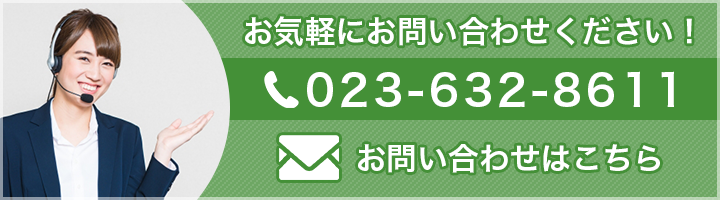

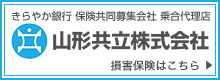
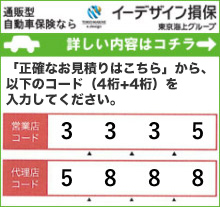





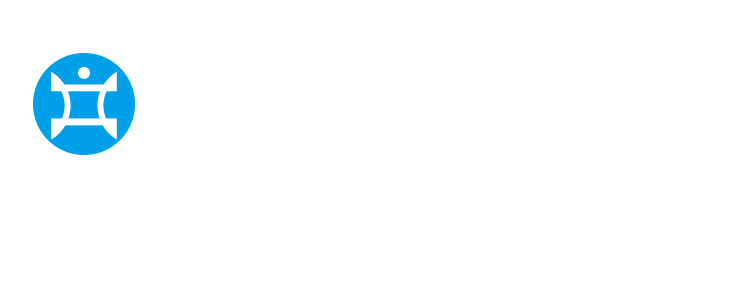 〒990-0042 山形市七日町二丁目6番3号
〒990-0042 山形市七日町二丁目6番3号